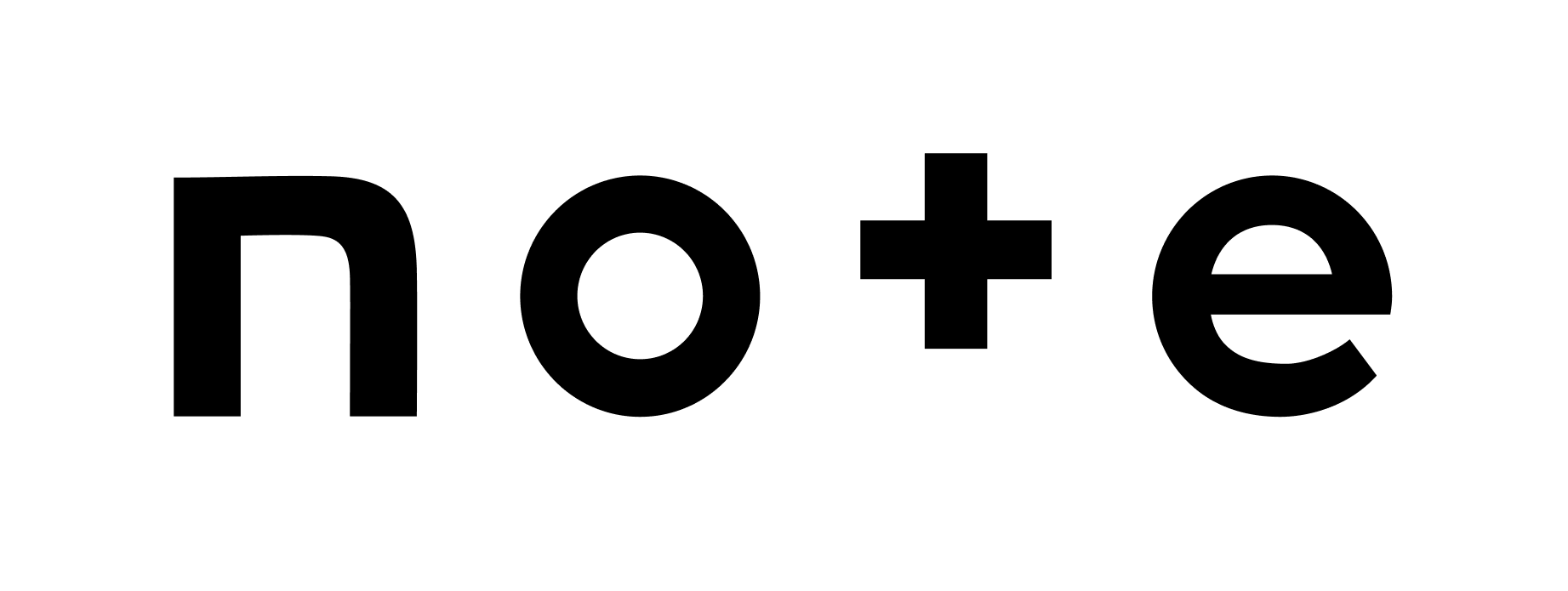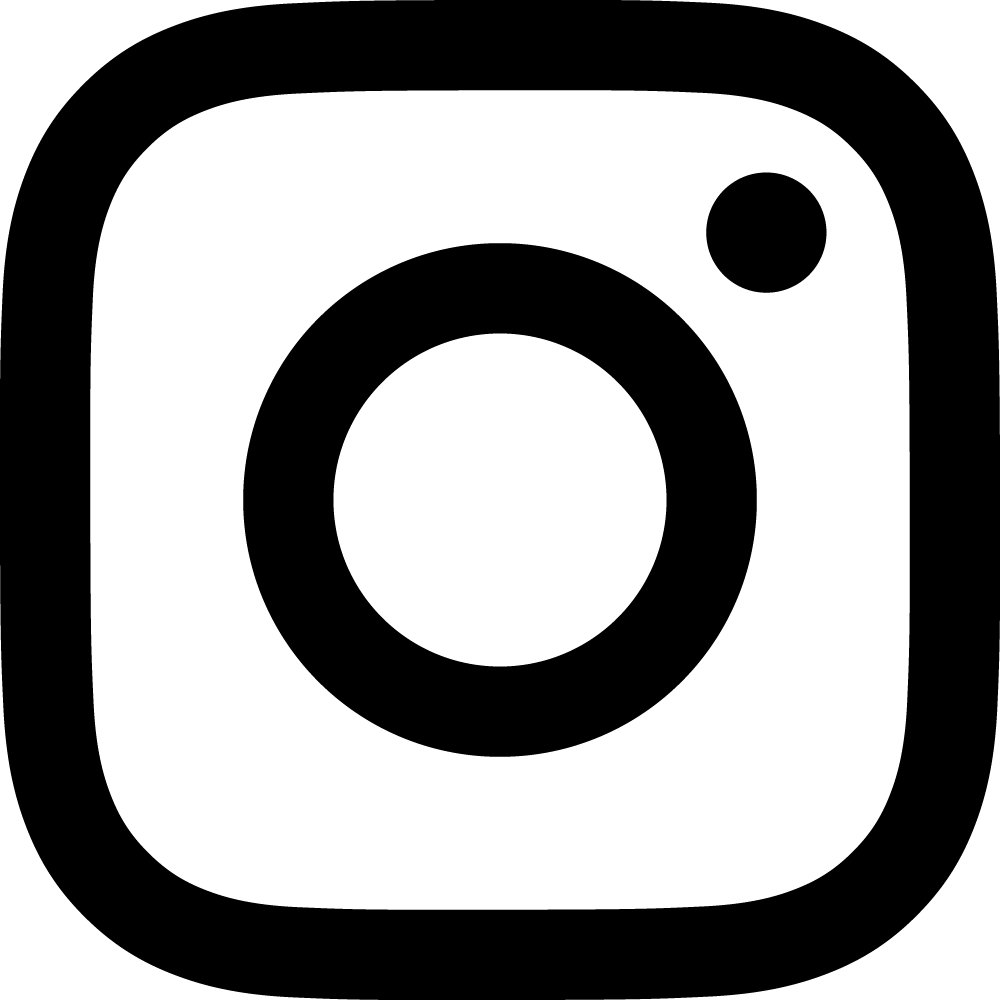コンサルティング部門
2024年入社(キャリア)
齋藤 純一郎
エンジニアとしてキャリアをスタートし、外資系コンサルティングファームを経て2024年LTSへ入社。現在はEA事業部で部長を担当。
コンサルタントとエンジニア両面の経験を強みに、長年に渡りIT戦略やエンタープライズアーキテクチャ策定、全社データ戦略策定の支援を経験している。
SEからエンタープライズアーキテクトへ “良い設計”への想いを貫いたこれまでのキャリア

私は、2024年5月にLTSに入社しました。近年の専門領域はIT戦略やエンタープライズアーキテクチャ策定等ですが、キャリアのスタートは300人程のソフトウェアハウスのSEでした。システムの保守運用業務や新卒採用等を経験した後、大手総合コンサルティングファームに転職し、保守運用に継続して従事する一方、オフショアリング等クライアント企業の保守運用業務標準化、ITコスト削減をミッションとした業務も担いました。
そしてキャリア11年目に独立系コンサルティングファームに転職しました。クライアントのシステム運用保守に携わる中で、障害の原因特定が困難、多くの手作業がないと動かない俗に言う「運用でカバー」する状況、極めてレスポンスが悪く業務ユーザーから苦情が絶えない等の、ひとことで言えば“イマイチな設計”のシステムを数多くみてきました。そのような保守運用者の視点を“設計”にフィードバックすれば、“より良い設計”のITシステムを構築できるのではないか、その実現をリードするような役割を担いたいと考え、コンサルティング業務に軸足をシフトすることにしました。
このコンサルティングファームでは、幸運にもお客様の基幹システム刷新プロジェクトに最初期から参画することができました。既存システムの分析から始まり、次期システムの構想策定、そして要件定義から稼働直後のサポート・初期流動対応まで、基幹システム刷新のエンドツーエンドの工程を、コンサルタント、ユーザー企業(発注者)側のPMOとして経験しました。大手SIerとの協業や、さらにはサービスイン後のユーザー対応を通じてITシステムがその開発を通じて内包する「物語」を深く理解でき、多くの学びを得ることができましたし、同時に悔しさも味わいました。
独立系コンサルティングファームに在籍した5年間の大半をこの基幹システム刷新プロジェクトで過ごし、サービスインを見届けてから、大手グローバルテクノロジー企業に転職をしました。この企業では様々な業界のお客様のIT戦略やエンタープライズアーキテクチャ策定、ITガバナンス体制構築や全社データ戦略等の様々な構想策定業務に従事しました。
このときの転職の理由は、先ほど申し上げた「悔しさ」にあります。前職の独立系コンサルティングファームはエンジニアリング部隊を持っていなかったため、開発は必然的にSIerにお願いせざるを得ませんでした。お客様がシステム開発をSIerに外注する過程で、設計思想となるクライアントや私たちコンサルタントが設計に込めた狙いや想い・願いが減衰し、換骨奪胎されていく様子を目の当たりにし、忸怩たる思いをしました。“より良い設計”を追求したITシステムを、同じ思想を共有するチームで実装しサービス提供したい、そのような一気通貫の体制を実現できる環境を求めていました。実際、いくつかの案件では、構想を社内のエンジニアリング部隊へ引継ぎ、システム構築を自社で実現することができました。もちろん、うまくいくことばかりではありませんでしたが、良い経験となりました。
このようなキャリアを通じて私が形成してきた価値観であり、仕事において常に重視していることは“良い設計”を追求するという点です。エンタープライズITの文脈で「設計」というと、多くの場合、「ITシステムの設計」(基本設計や詳細設計)と捉える方が多いと思いますが、私はより広範かつ汎用的な概念として捉えています。
たとえば、世の中に「〇〇戦略策定」と名のつくコンサルティングプロジェクトは数多あると思いますが、既存のフレームワークや過去の事例の「どれを下敷きにするか」を「選択」することから始まるような、最も悪いケースではその「選択」がゴールになるケースが散見されます。本来であれば、戦略策定こそ最も「設計」余地の大きな活動であり、フレームワークや事例はそれを補完する存在でしかないはずです。
私が考える“良い設計”とは、既存の要素を単に組み合わせたり当てはめたりするのとは対極にある活動です。積み重ねてきた知見とクライアント企業への想いを土台として、現状に深く潜りこみ、もがいた上で導かれる「上澄み」のようなもので、たとえ結論が一見ありふれたもののように見えたとしても、その導出過程は毎回異なるものであるべきだと考えています。そうでなければ、その「設計」は多くの人を動かす説得力、必然性を持ち得ないと思います。振り返ってみると、私のキャリアは“良い設計”を追求したいという想いに突き動かされてきたと言えるかもしれません。
クライアントへの提供価値を追求できる環境を求め、LTSへ
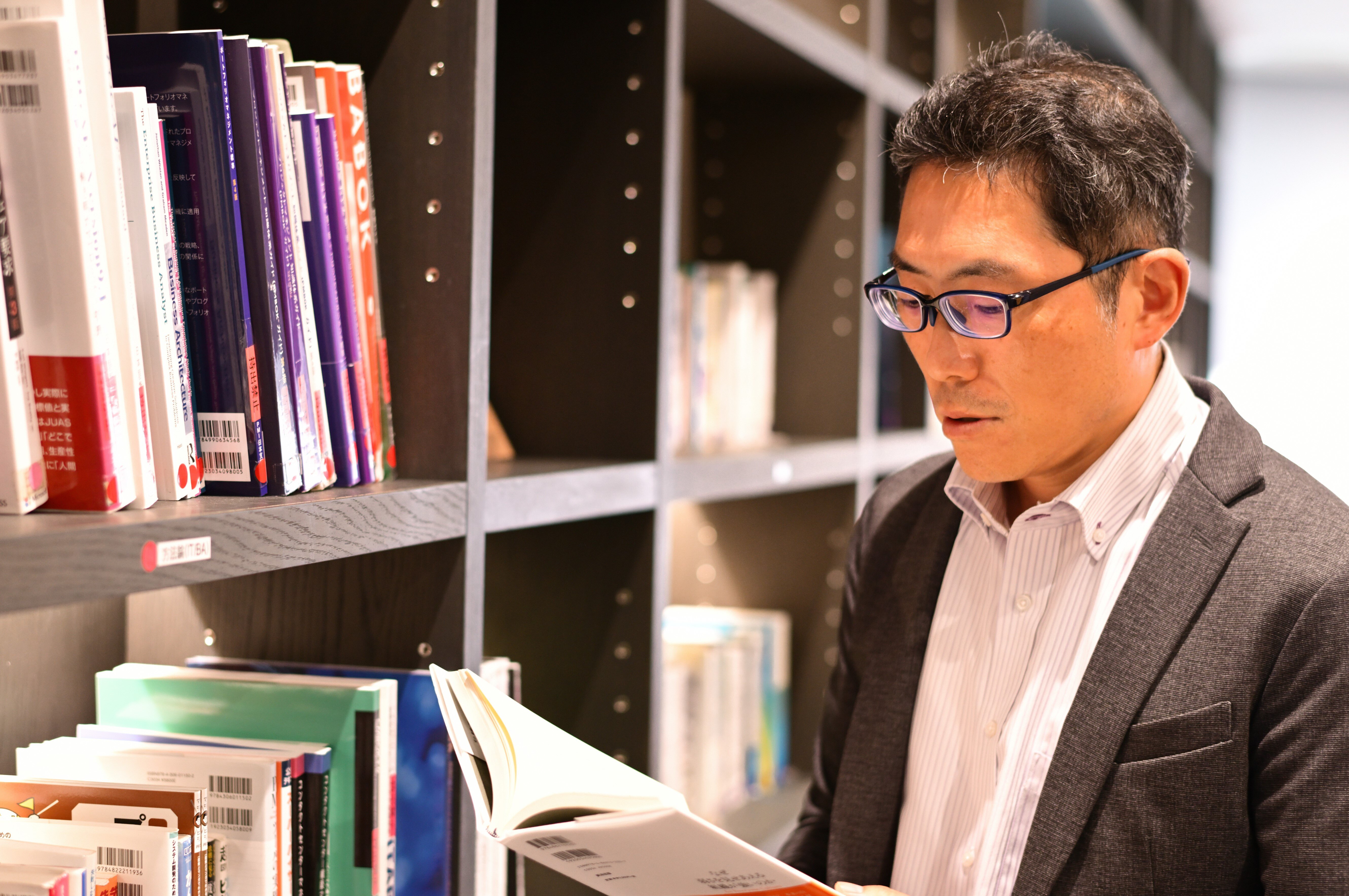
大手グローバルテクノロジー企業での経験は、日本を代表する多くの大企業の方々との協業の機会を得たり、豊富な方法論を学ぶ機会に恵まれたり、何より本当に優秀な上司・同僚・若手の方々から常に刺激をもらえ、非常に充実したものでした。ただ、私は本来的には「限られたリソースでいかに戦うか」を得意とするタイプで、潤沢なリソースを活かした戦い方、ちょっと露悪的な言い方をすると大艦巨砲主義的な大企業ならではの戦い方とのズレが、期待される役割の変化と相まって徐々に大きくなってきていました。
「大きな看板に頼るのではなく、自分のケイパビリティを頼りに戦いたい」と考えていたときに出会ったのがLTSです。経営層との面談を通じて感じた組織の若々しさと貪欲なまでの成長への欲求は、可能性の塊でとても眩しく感じました。この人たちと、共に机を並べて働きたいと強く思いました。
私自身、これといった特長もなく、「ない袖は振れない」中でどうするかを考え、生きる道を見つけてきたようなところがあります。
LTSの経営層の発言や眼差しから感じたのは上場や創業20周年といったマイルストーンに安住せず、チャレンジャーとして革新を志向する姿勢でした。このような企業こそが成長し、社会に対して大きな影響力を持つべきだと素直に思いましたし、そこに自分なりの貢献をしたいと思い、入社を決意しました。
現在はコンサルティング業務と並行して、Digital Consulting事業部の副部長(24年度組織名および役職)として、組織の成長戦略策定、人材育成、ナレッジの高度化等に取り組み始めたところです。
また、同事業部を統括するDigital事業本部は、コンサルタントとエンジニアがほぼ同数在籍する混成組織です。多様な専門性を持つプロフェッショナルが結集し、クライアントにEnd to Endの価値提供を実現することを目指し2024年1月に立ち上がったと聞いています。
私自身のキャリアもソフトウェアエンジニアリングとコンサルティングの両方にまたがっており、2つの領域を効果的に融合させる上で、ちょうど良いポジションにいると感じています。この強みを活かし、当事業本部が掲げるビジョンの実現に向けて取り組んでいきたいと思っています。
教育だけでは得ることが難しいカルチャーの特徴を競争力に転化する

入社後のLTSの印象ですが、最初に感じたのは、社員にちょっとした周囲への気配りがあることでした。エントランスで出入り口のドアを手で開けて待っていてくれたり、エレベーターで私を先に通してくれたりする。当たり前と言えば当たり前の行動かもしれませんが、こうした配慮は教えられて身に付くものではありませんし、これをホテル業や小売業ではなく、コンサルタントやエンジニアがやっていることに、驚きとともに嬉しさを感じました。特に若い社員たちが自然に実践していることに、LTSのカルチャーが滲み出ているように感じます。なんとはなしに広く周りを見渡して気を配れる、清々しい人が多い。そして若い(笑)。
こうしたLTSが持つカルチャーは、“良い設計”を追求する上でも大きな武器になると考えています。著名なソフトウェアアーキテクトの言葉を借りれば、ソフトウェアアーキテクチャの価値(≒“良い設計”の価値)とは「変更コストの最小化」だと言います。これをSIerやコンサルティング会社の視点から見れば、ソフトウェアの変更≒収益機会ですので、短期的にはむしろ収益機会を奪うようにみえます。しかし、長期的には変化対応力が高い、変更コストが低くすぐに変更できるようなITシステムが、クライアント企業がより高い付加価値(≒収益)を創出することに貢献するはずですし、そのような貢献に対し、SIerやコンサルティング会社に対し新たなビジネス機会がフィードバックされるーこれこそがあるべきビジネスモデルだと考えています。
このようなビジネスモデルを本気で実現する上で不可欠なのが、自らの提案がクライアント企業にとって最も価値をもたらすはずである、そして自社のビジネスはクライアント企業の付加価値創出の増分に付随するものである、という少し長い時間軸に基づく視座と強い信念です。これは職業教育だけで得られるものではないと私は考えています。LTSには、将来を見据えながら真の価値を追求できる資質を持った人財が数多く在籍している、私の目にはそのように映っています。
一方で、まだまだ未成熟な面もたくさんあると思っています。現時点では、ナレッジやノウハウの蓄積、方法論の習熟においては、グローバルに展開している大企業と比べると大いにテコ入れの余地があると思っています。ただLTSという組織が持つ潜在能力はとても高い。その潜在能力を最大限に引き出し、組織全体の競争力を高めていくことが、私の重要なミッションだと考えています。
クライアントへの価値提供と戦略的成長の両立を目指して
そういった状況をふまえ、今後の優先課題として、ナレッジの体系化や高度化、トレーニングプログラムの拡充等に着手していきたいと考えています。そして、クライアント企業に高い価値を感じていただくことが大前提ですが、LTSにとってさらなる成長のきっかけとなるような戦略的案件を獲得・創出していくことも欠かせません。まずはそこで私自身がしっかりと成果を出していきたいですね。
キャリア入社という立場で感じているLTSの魅力は、これまでに培った経験や創意工夫する力を存分に発揮できる環境があることです。年齢・経験を問わず、やりたいこと、発揮したいことを持っているチャレンジ精神を持つ方々に対してその実現をサポートする、そんな会社です。
キャリアにおいて、組織やサービス、ブランドの構築に深く関わる機会に巡り合えるのは本当に幸運ですし、それだけで貴重な機会ですが、その実現を本気で後押ししてくれる会社はそう多くはないと思います。
ここまで申し上げたような環境、カルチャーが肌に合うと感じる人財にジョインしてほしいですし、そのような方々と一緒に仕事ができることを楽しみにしています。
※ 記載内容は2024年8月時点のものです。