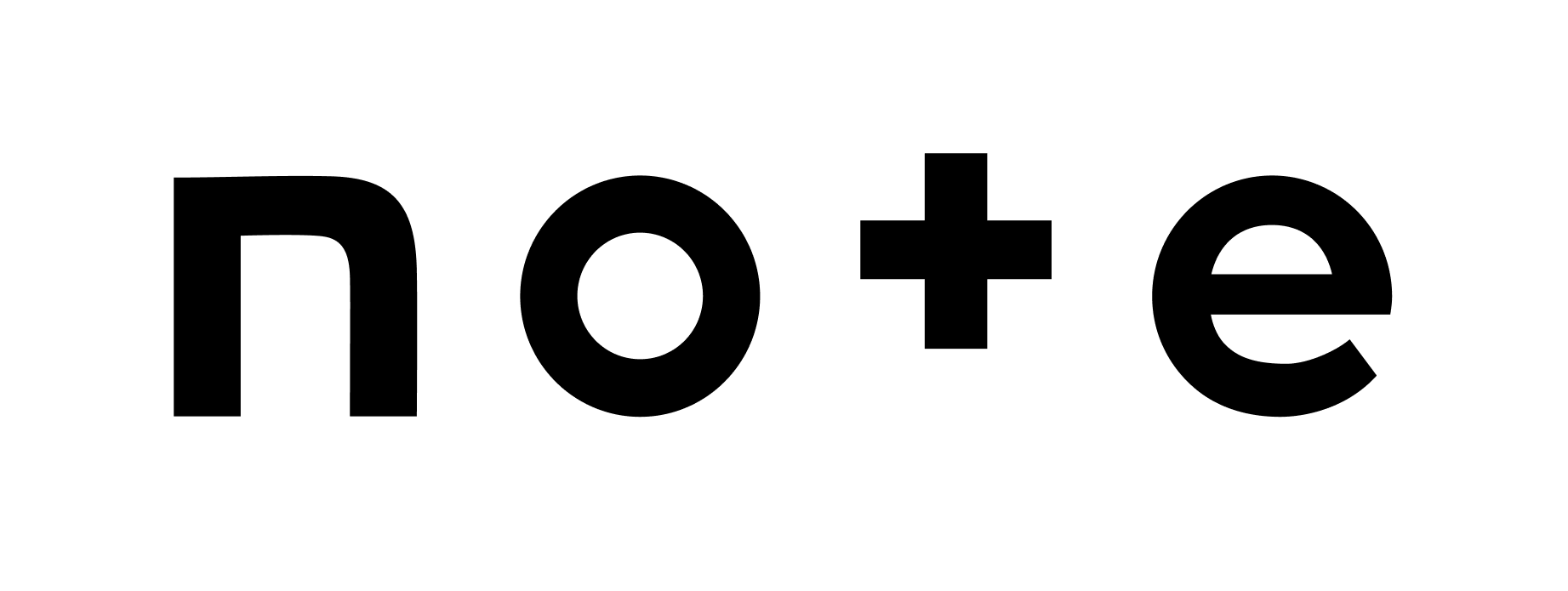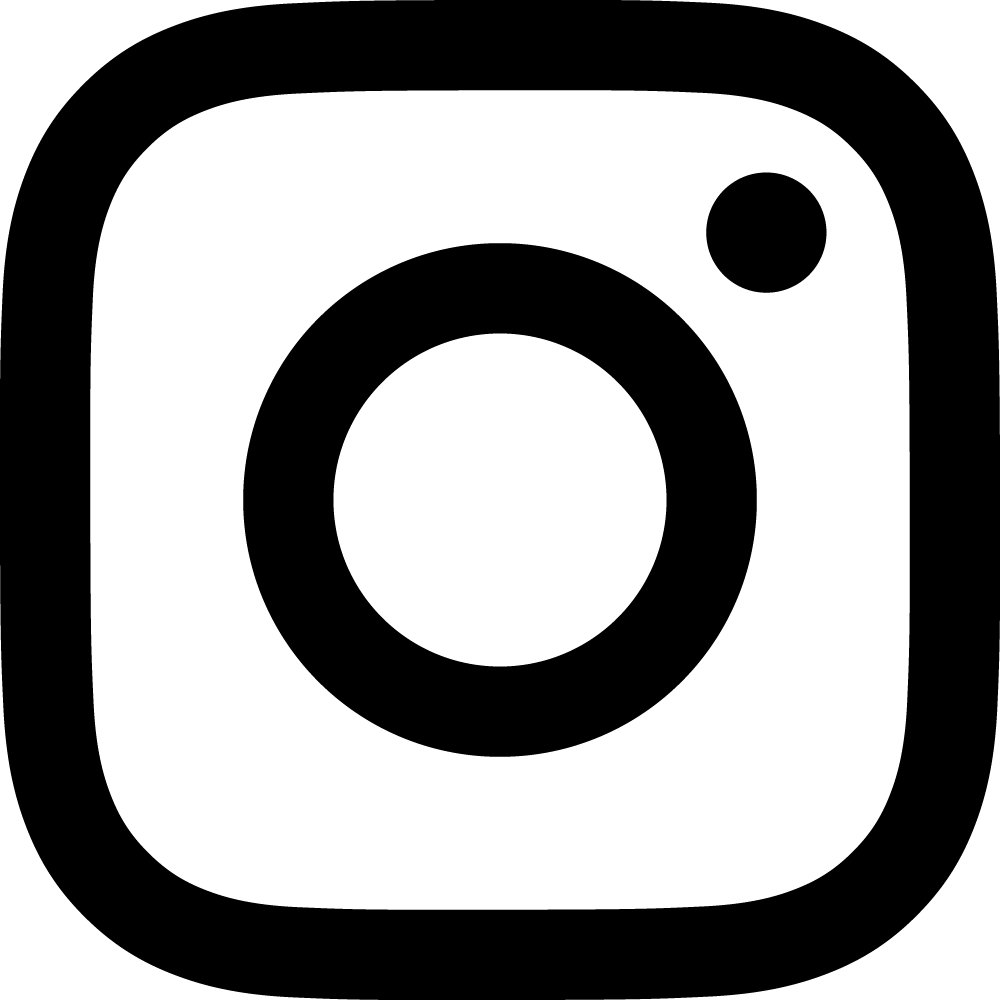エンジニア部門
2021年入社(キャリア)
田中 遥介
新卒でヘルスケア領域に強みを持つSIerに入社し、フィールドエンジニアを担当。現場課題のヒアリングや業務改善にやりがいを感じていた一方で、自社サービスを持つ企業でスピーディーにクライアントの開発要望に応えられるようになりたいと考え、専門学校でプログラミングを学びLTSへ転職。入社後、自社サービスも含めたインフラ運用・保守およびシステム開発を担当している。
1つのチームとして成長するための創意工夫

現在、私はDigital事業本部 Cloud Integration 事業部(24年度組織名)に所属しています。部署全体で約60名が在籍し、多岐にわたるサービスを提供しています。私の主な担当はクラウド開発とシステムのアプリ開発で、直近では異なるクラウド環境を使用している2つのプロジェクトに参画しています。
そのうちの1つは広告代理店様の運用支援システムの運用保守業務です。AWS環境下でのインフラ運用保守なのですが、これまで運用の体制が十分に組めず、課題の整理が必要となったタイミングでLTSが入らせていただき、同業務を1年以上お任せいただいています。
もう一方は建設コンサルの企業様の施設管理システムの新規開発です。Azureでのサーバー構築やCI/CD環境の構築を行っており、リリースに向けてタスクを進めているところです。
どちらのプロジェクトも、過程において重視していることはドキュメント化と自動化です。ドキュメントがないと、作業時に確認工数が余分に発生したり、ミスが起こりやすくなったりします。また新たなメンバーが入った際の業務習得のスピードにも大きな影響を与えますので、開発におけるドキュメントをきちんと可視化しながら進めることを常に意識しています。
合わせて業務を自動化できるものがないかを検討し、可能な項目は自らプログラムを作成してチーム全体に展開しています。この両軸を進めることで、業務の属人化を回避することができ、安定稼働に繋がると考えています。
私のチームには新卒入社の方もアサインされていて、平均年齢は30歳前後と、比較的若い方が多く活躍しています。
雰囲気が良く、先輩・後輩問わずコミュニケーションが活発な印象ですが、若手メンバーが多いことを考慮すると上記のようなドキュメント化や自動化がチームのパフォーマンスに寄与するのではと考えています。
また、私はチームの中で比較的上の年代に入るので、若手メンバーのサポートを積極的に行うように心掛けています。効率的な業務遂行のためにどう動けばよいか、といった具体的なアドバイスや、若手の皆さんが先輩に気軽に声をかけられるように話し方や雰囲気作りを意識して、心理的なハードルを下げるようにしています。そういったコミュニケーションの中で、メンバーが困っていることが少しでも解消していたら嬉しいですし、1つのチームとして一緒に成長していきたいですね。
自分の手で顧客要望に応えたい エンジニアとしての歩み

大学時代は情報通信工学を専攻し、認知工学と脳科学の観点からヒューマンエラーに関する研究を行っていました。もともとPCに興味があって学びを深めようという理由で、脳科学の研究を担当している教授と親しくなったのですが、その教授のキャラクターがとても魅力的で、人柄に惹かれて研究室を選びました。研究室では、テトリスをプレイする際の眼球運動、心拍数、キーストロークを測定し、難易度の変化に伴う人間の反応を調査しました。人によって反応の仕方が異なるのですが、非常に興味深い研究結果を得られました。
この研究から、スポーツや医療系の分野への興味が深まっていきました。同時にITにも関心があったので、これらを掛け合わせた仕事ができたらいいなと考えて就職活動を行い、健康診断システムをパッケージ販売しているSIer企業とご縁があり、入社を決めました。
その会社では、システムの利用ユーザーの操作支援やマスター整備等を担当するフィールドエンジニアとしてキャリアをスタートしました。現場の課題をヒアリングして業務改善に取り組む仕事にやりがいを感じていたのですが、クライアント要望を開発部に伝えてシステムに反映する、という工程は時間がかかってしまうことが多く、すぐにご要望に沿えないことにジレンマを感じるようになったのです。もっとスピーディーに要望に応えられるようになりたい、他部門に任せるのではなく自分の手で解決に導けるようになりたいと思い、システム開発まで行えるエンジニアとして転職をすることを決めました。そのためには最低限プログラミングスキルが必要と考え、専門学校に通って基礎的な知識・技術を学び、転職活動を行いました。
LTSに出会ったのは、専門学校の友人の紹介です。転職先として自社サービスを持つ企業をイメージしていたところ、友人がLTSに内定をもらっていて、私のことを紹介してくれました。自社サービスを持っていることと、「LTSの社員は皆いい人で、知識を貪欲に学ぶ姿勢を持っている」と友人から聞いていて、働く環境の良さが感じられたことが決め手となりました。
実際に入社してみて、社員の方々は本当に優しくて、積極的に情報を獲得していく姿勢を持っている、イメージ通りの環境で、入社前後のギャップは感じませんでした。
LTSでは、まずは自社サービスであるマッチングプラットフォームやDX事例紹介メディアの開発に携わりました。自社のサービスのため、じっくりと案件に向き合うことができ、必要な技術全般を学ぶことができた期間でしたね。その後、現在の受託開発の仕事を担当するようになったのですが、その中で印象に残っているのは「早く行くなら一人で、遠くに行くなら皆で」という先輩の言葉です。スピードだけで考えると、自分がやってしまった方が早いことはたくさんありますが、より良いもの、さらに大きなことを成し遂げるためにはチーム全体で取り組むことが必要だ、という意味です。開発の仕事はチームで取り組み、チームで成果を出すことが求められるわけですから、この言葉は心に刺さりました。
以降はチームとして成果を出すために、効率化を目的とした業務用プログラムやドキュメントを作って若手メンバーが勿体ない躓き方をしないようにフォローする等、チーム全体のパフォーマンスが上がるような関わり方が自然な動作になっていきました。こういったチーム志向というか、全体でボトムアップしていこう、という意識は、私自身のコアとなる考えになっていますが、同時にLTS全体の共通認識のようにも感じています。
自己成長の先で、一人では得られないチームとしての大きな達成感を抱く

LTS入社後、特に印象に残っている仕事の場面は、初めて複数のプロジェクトを掛け持ちした時のことです。受託案件のCRM開発と自社案件を同時に担当することになったのですが、自身のパワーの配分に戸惑い、どちらの業務のどのプロセスにどれくらいの工数を使うのか、といった調整に苦心していました。加えて、受託案件では知見のないサービスを使用していたため、並行して情報のキャッチアップも必要となり、時間に追われていた記憶があります。当時は知識を得ようと、休日も書籍から学びを得たり、自ら外部のエンジニアの勉強会やコミュニティに参加したりして、ネックとなっていた知識不足を補っていましたね。
大変ではあったのですが、ありがたいことに勉強が苦にならないタイプで、自分ができないこと・知らないことを学んで、それができるようになることがモチベーションになっていました。自分の武器が増えたことを喜ぶ気持ちでキャッチアップを進めることができ、プロジェクトも無事に終えることができました。
また、上記プロジェクトの他、2022年に新卒2名の教育を担当した時のことも印象深いです。
効果的・効率的に成長してもらう方法を考え、オンラインビデオを使用してペアプログラミングのような形で指導したり、アジャイル開発を取り入れて2週間に1回リリースをする形で随時テストを行ったり、自分なりに工夫をして取り組んだのですが、最終的に、経験のある方2~3名で通常2カ月かかるような業務を、新卒2名の方と私の3名体制で1カ月程度で完了させることができました。新卒メンバー2名の頑張りもあって、不具合もなく短期間で完了できたことに、チームとして大きな達成感を持ちました。
振り返ってみると、私が達成感ややりがいを感じるのは、自分の行動によって他の人のパフォーマンスが上がった時が多いように思います。プロジェクトで開発効率を上げるプログラムを作成しているというお話をしましたが、それをメンバーが使って成果を出せた時に、貢献できているという実感がありますし、自分のモチベーション向上に繋がっています。
挑戦を通じて個が育ちチームが強くなる 私が描くこれからのキャリア
今後のビジョンとして、特定のパブリッククラウド(AWS, Azure等)に依存せず、サービスの信頼性強化を目的に、SRE(サイト信頼性エンジニアリング)を軸にキャリアを積んでいきます。SREの主要スキルである可観測性、自動化、エラー予測、アラート設計を体系的に習得し、サービス全体の信頼性を高めるエンジニアリング手法を確立することを目指しています。
また、LTSのエンジニアの中では中堅と言える立場として、引き続きメンバーの成長を見守りたいですし、その挑戦の手助けをしていくことは変わらず実施していきたいです。挑戦を通じて個が成長し、チームとしてできることが増えていく、そしてチーム全体でメンバーを支え合う、そんな環境を作っていきたいですね。
LTSにおいては、エンジニアと言ってもクライアントに提案をすることもありますし、担当フェーズを拡げることも求められていきます。自分の幅を拡げるためには新しい情報に触れ、血肉にする必要があるため、学ぶことが好きでないと苦しくなる仕事だと感じています。学び続ける覚悟や楽しむ気持ちがないと、最初は気合いで頑張ることができたとしても、途中で息切れしてしまうかもしれません。
ですから、エンジニアを志向する方に大切にしてほしいのは、ワクワクしながら知見を広げていくこと。周りが与えてくれるのを待つのではなく、自ら動いて掴んでいくこと。そういった考えに共感して実践できる方と一緒に働けたら嬉しいですね。
※ 記載内容は2024年9月時点のものです。